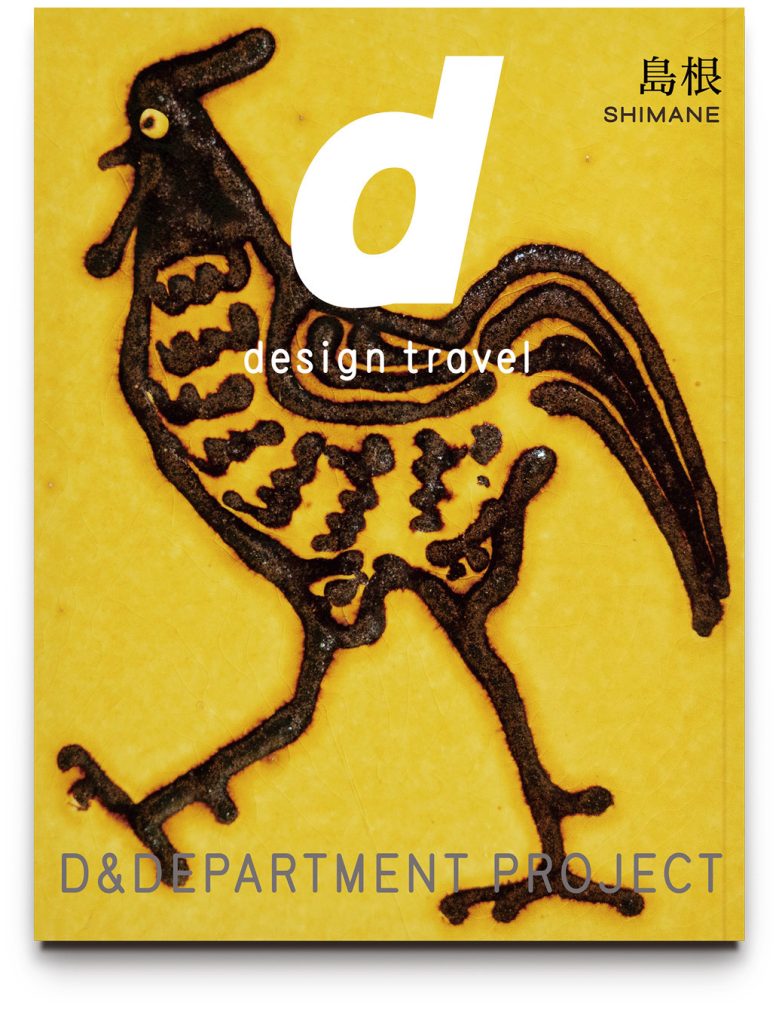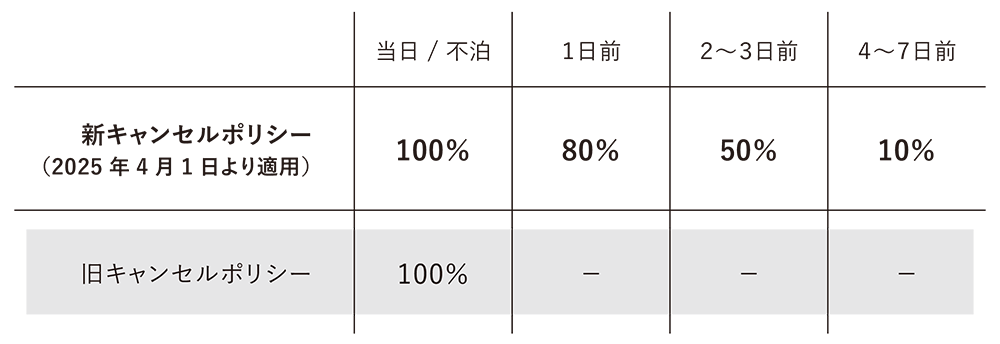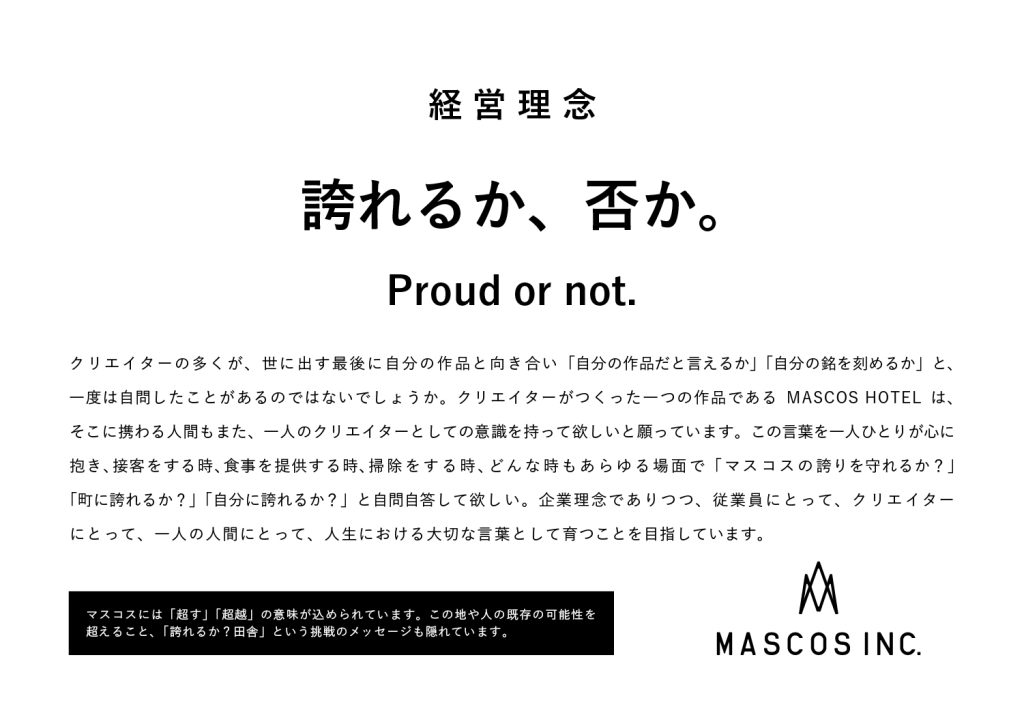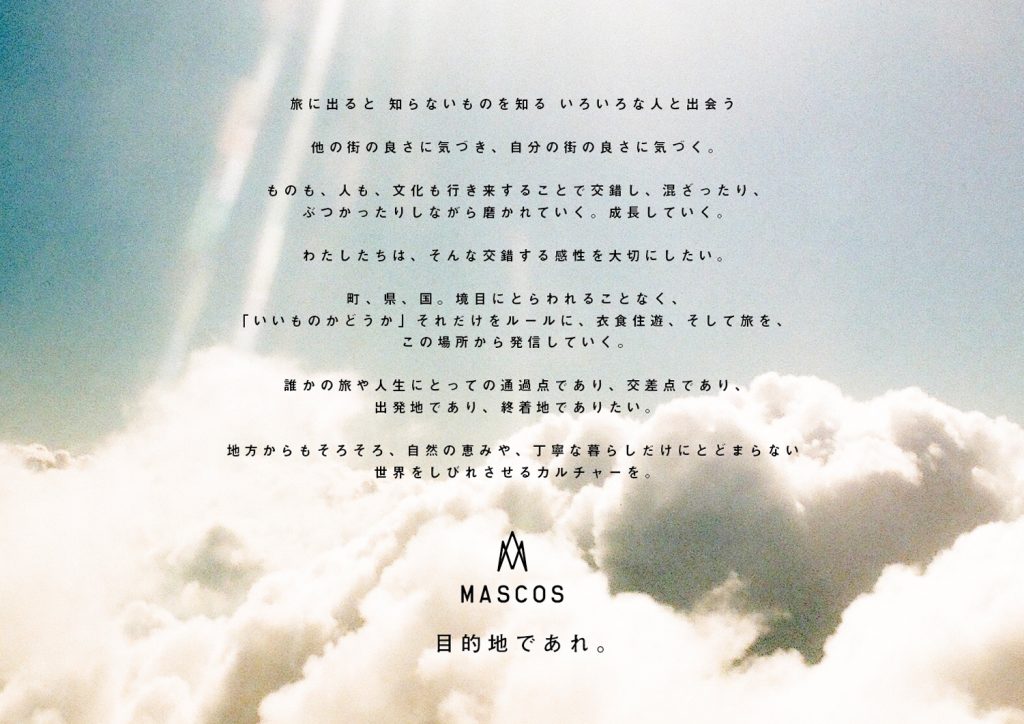MASCOS INC. 社長の洪 昌督(こう しょうとく)です。前回の記事でも触れたMASCOS AGORAの第2回目は、地域研究の第一人者・藤山 浩(ふじやま こう)さんをお招きして開催しました。

藤山さんのテーマとする地域課題というと、どうしても行政機関の管轄とされがちですが、私は民間の方々にも広く藤山さんの存在や考えを知っていただきたいという思いがありました。その意味で、今回は少しその願いが形になったように感じています。結果として、参加者の皆様には多くの学びと気づきがあったのではないでしょうか。
「地域循環型社会」とは何か。そして、それを実現するためのステップについて、人口動態データや購買データをもとに、今回藤山さんが理論を展開してくださったことで、強く納得・共感する場面が幾度もありました。
島根県益田市に本社を置き、地元で経済活動を行う私たちのような企業にとって、地域内でお金が循環しなければ、その存在意義すら問われかねません。経営者の視点から見ればごく当然のことですが、現実として多くのお金は、県外に本社を構えるチェーン店やフランチャイズ本部へと流れていきます。
さらに、飲食店や小売業者の多くが域外から仕入れているという事実は、人口減少以上に私の心に残りました。
少し古いデータにはなりますが、仮に益田市周辺を「高津川流域経済圏」と呼ぶならば、その人口は当時約7万人。そして年間の域外調達総額は約1,420億円にのぼるとのこと。これは、域内の住民の年間所得総額である1,556億円に匹敵する金額です。
つまり、地元で稼いだお金の多くが、最終的には外に出ていく構造ができあがっており、事実上これでは「地域循環」とは到底呼べません。
もちろん、「選ばれない企業」が競争に敗れたのだと言ってしまえば、それまでのことです。しかし、地域を深く知れば知るほど、そのような単純な話ではないことに気づかされます。
何を「良し」とするのか、その尺度や価値観が、地域経済のあり方に強く影響しているのです。つまり、個の価値観がダイレクトに地域経済に影響しているとも言えるでしょう。
たとえば、益田市は石見地方に属し、ここで有名なのが別名「赤瓦」と呼ばれる赤褐色の「石州瓦」です。島根県芸術文化センター・グラントワの建材としても使われているこの瓦は、1350度という高温で焼き締められ、世界でも屈指の強度を誇る建材です。そして、この赤瓦を屋根に使った家々が、地域特有の美しい景観を形づくってきました。

しかし近年、イニシャルコストの問題やデザインに対する価値観の多様化により、赤瓦を用いた新築はほとんど見かけなくなりました。益田市でも、コロナ禍以降の住宅建築ラッシュのなかで、赤瓦の家はほとんど建てられていません。
その結果、1995年には28事業所あった地域の伝統技術を担う瓦製造事業所は、現在では石見エリアに4ヶ所のみとなり、実際に工場として稼働しているのは、浜田市・江津市・大田市にそれぞれ1社ずつ残るのみとなっています。益田市からは、すでに姿を消してしまった状況です。
これを「競争に敗れた」と片づけてしまって良いのでしょうか。地域には、それぞれの気質や暮らし、価値観があり、それが長い年月をかけて独自の文化として育まれてきたのです。

現在、日本の観光市場はインバウンド需要で活況を呈しています。これは単に円安の影響だけではなく、日本独自の文化や風景に魅了されて訪れる外国人が多いからではないでしょうか。
益田市にも、益田市ならではの「らしさ」が確かに存在します。
しかし、それが少しずつ失われていくなかで、この土地で生きていくことは、私のように文化や芸術を愛する者にとっては、あまりにもシニカルに感じられるのです。
もちろん、その儚さに美を見出すという視点もあるでしょう。でも、私はこの土地で生きる者として、儚さに抗いながらも、自分にできる最大限のことをしていきたいと考えています。
藤山さんの言葉でとりわけ印象に残ったのが、「1%の力」という考え方でした。
地域に暮らす一人ひとりが、たった1%でも行動を変えるだけで、地域経済は確実に変化するのです。母数を1500億円とすれば単純計算で15億円の経済効果が域内に生じることになります。
たとえば、外資系スーパーに年間100回通う人が、たった1回だけでも地元のスーパーに足を運ぶ。というそれだけで、地域循環の流れは生まれます。この地には早くから地域循環を実践し、地産地消の草分け的存在のキヌヤさんという素晴らしいスーパーがあります。

私がローカルコンセプトのマスコスホテルを始めたのも、このブログを始めたのも、そんな小さな一歩を信じてのことです。
そして、かつて私自身が地域経済や地元の文化の魅力に全く気づけていなかったことを、今となっては恥ずかしくも感じます。
「無知は罪だ」と言われることがあります。確かにその通りだと思う部分もありますが、人間は本質的に未熟であり、誰かが無知であることには、むしろその先人や周囲の責任もあるのではないかと思うようになりました。
私を含め、この地を離れて活躍している人も、そうでない人も、もしもっと早く、もっと深く、地域のことを教え、伝えられていたならば、今のように安さを売りにした外資系のチェーン店に地域の人々が群がる状況にはなっていなかったかもしれません。
風前の灯火のような今の現状に対して、「既に遅い」と言われるかもしれません。それでも私は、自分なりにできることを、少しずつでも言葉にして、誰かに届けていけたらと思っています。